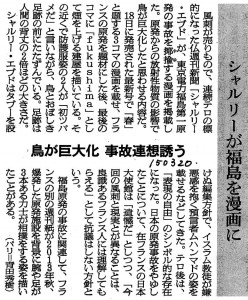●日本の教育改革の中核にいる人物を知ろうと、本書を手に取るが、選書を誤った? 表面的な掛け声が繰り返されるだけで、具体的な部分は見えてこない。飛行機乗ってあっちゃこっちゃ行って、自分がグローバルな気分を満喫しているだけの本? まだ途中までしか読んでないけど、恐ろしくつまらない。教育についても、「私学に金をくれ!」というメッセージしかなかなか読み取れない。大丈夫か、日本!!!
同じ著者の別の本ならもしかして・・・と思わないこともないが、もっと何かあるのなら、それは本書にも滲み出るはず。
つまらないハードカバーの本を買って読むほどつまらないことはない。その怒りが本の評価をさらに下げる・・・
いやいや、まだまだ最後まで読むうちに、珠玉のエッセンスに出会えるかもしれない。がんばりましょう。
============(メモ)============
159-
<どんな人材を育てるのか>
知的な努力によってオリジナルな成果を挙げるという経験と訓練を積んだ人間159
グローバリズムの中で、政治・経済・文化すべて背景や価値観の違う人々とつきあわなければならない。自分で考え自分で行動すべき時代になったということだ。その基盤が教養であり学問である。172
(スポーツ中継)声の大きさに囚われずに内容を理解し、批判も含めた合理的な分析と評価を常に心がける態度を身につけることは、好む好まざるにかかわらずグローバリズムの潮流に巻き込まれた日本と日本人にとって、きわめて重要なことである。181
大学で学ぶべき大切なことは、まず自分で考えることである。……人の言うことを鵜呑みにせず、自分で考え、その考えを学問に照らして深く大きくしていく。184
新しい日本のための成熟した民主社会を担う、権威に寄りかかることのない人間を、一人でも多く育むことである。それには全国の平均的な大学生に、独立して生きる力と、お互いに協力して生きる力を、本格的な教養として身につけされることが必要であり、それを学べるようにすることが今の日本の大学の果たすべき責務なのである。197
平均的大学生の質を向上させる209
<大学>
大学は……「独立」(independence)と「協生」(collaboration)の二つの焦点を常に持つことが必要199
大学もまた社会的使命感を持つべきである。教育や研究も含まれるが、これからの大学には特に、国際社会や地域社会の長期的な課題を見出し解決していく使命がある。─改行─とりわけ、国際的に活動できる大学の場合は、グローバリズムの潮流とともにあぶり出されてきた困難な課題(グローバル・イッシュー)、たとえば気候変動、エネルギー・環境・経済の相互関係、食糧や水資源の危機、貧困と国際紛争、生活と健康の安全保障、情報流通と知的財産権など多くの課題に、学術的立場から解決策を提言していく使命がある。207
<どんな教育をするのか>
自分で考え、自分の言葉に責任を持って他人と真剣に討論をする大学院教育160
心の底から涙が湧き出るような体験をすること(感動体験)165
日本の大学で何が学べるのか。その一つのポイントは、アジア諸国の中で、政治、経済、生活、環境、健康、教育、芸術、科学技術、その他の活動において、個人の自由と独立を重んじ、高い水準に達しつつある国、しかも、環太平洋地域にあって独自の文化を持つ国の大学だという点にある。……日本の大学はこうした人たちに応えられる内容をもっていかねばならない。193
<どんな社会をつくるのか>
明治以来続いてきた追いつき追い越せの途上国に留まるのでなく、オリジナルな発想によってグローバル社会に貢献する国162
日本の新しい社会、成熟した民主主義の社会
<今の教育の問題>
今必要なのは、高校生がそれぞれに十分な体験と情報を享受でき、それに基づいて未来への夢を紡ぐことのできる、社会の多様な評価軸である。ところが一般に、高校生が自分の未来を考えるために得られる体験や情報は、大人が思うよりも遥かに少なく、……限定され過ぎている。これもまた、長年受け身の形式に慣らされてきた学校教育制度の限界ではないか。197
十二月初め、OECDのPISAの結果が発表され、日本のランクが下がったことが話題になった。報道などでは、これまでの「ゆとり教育」が学力低下を招きランクに影響した、という論調がもっぱらだった。広い意味で頭を使う時間が少なければ学力が低下することは、基本的にその通りで、一般的にいえば勉学の時間を増やす必要はある。ただし、頭を使うことと受け身でしかたなく勉強時間を消費することとは別で、自分から進んで勉強したいと思わなければ、いくら授業時間を形だけ増やしても意味がない。フィンランドの子どもたちは、授業時間が少ないのに学力評価が高いことはよく知られている。……日本の場合は、創造性を育むためにはおしつけの教育はダメだという考え方が、家庭や地域コミュニティへ/の生活支援政策とは無関係に、学習指導要領という形式であまりにも一律に制度化されて施行されたことのしわ寄せが、現場の先生方と子どもたちの方にいったことが大きい。205-6
「ゆとり教育」と学力低下とPISAの結果の関係は、したがって単純なものではない。たとえば、夢や目標を持てば意欲が湧き学力は上がるし、目標のない子どもは学力を上げる必要はなく学ぼうとしない方が当たり前である。……社会的使命感が大人の社会から消えつつあることと、子どもたちが目標を持たないこと、そして学力が低下しつつあることには、強い関係があるように思える。206
<今の大学生の問題>
今の大学生は元気がない、大学生の学力低下164
<今の社会>
多極化した世界、国内の多極化(地域、年齢層)、寄付や教育費負担などに関する税制改革、各地域の教育現場への権限と責任の異常など……187
<教養>
教養とは社会と断絶した趣味ではなく、独立した人間として他者と協力し生きていくために持つべき、広く深く血の通った思考の基盤、判断の基準のことである。教養を身につけるには、人類の知的遺産としての良質な古典を読破するのはもちろんだが、尊敬できる人間に出会い、自分をさらけ出す社会体験を積み、体験と他者と書物の間を何度も往復することが大切だ。大学はそのための拠点になることができる。167
基礎的な知識のうえに合理的想像力を磨くことが、教養への大きな一歩なのである。170